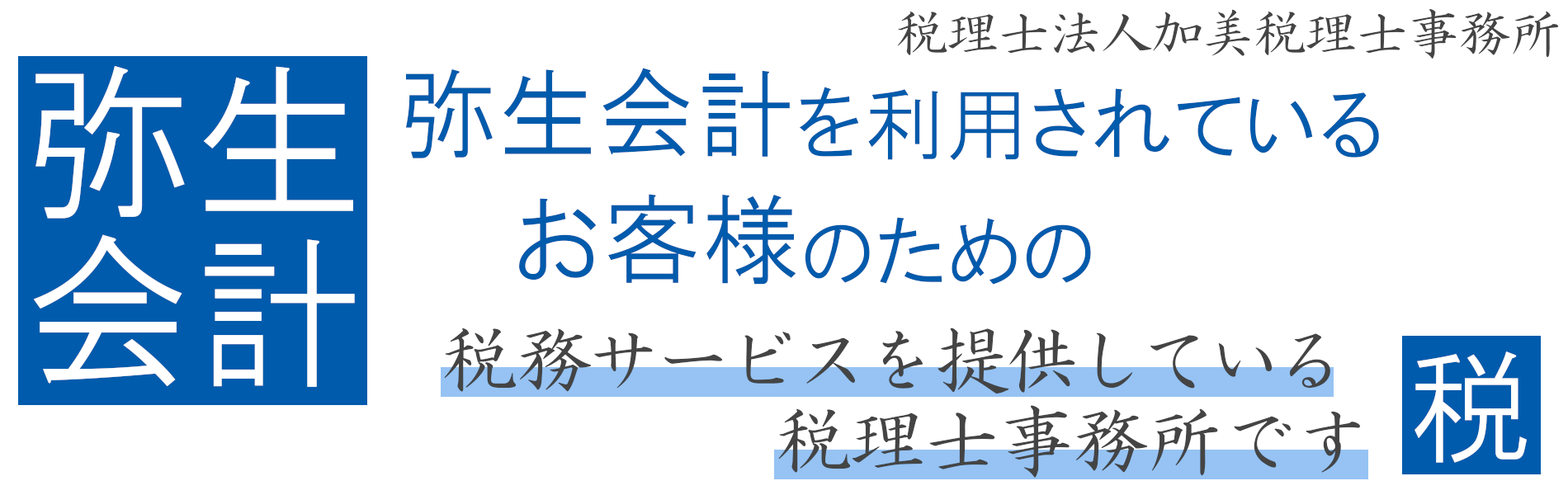ごあいさつ
弥生会計を得意としている税理士法人加美税理士事務所の税理士 川畑英之と申します。
こちらのウェブページにお越しいただき誠にありがとうございます。
税理士法人加美税理士事務所では、弥生会計を利用されている法人および個人のお客様の税務申告などを承っています。
当事務所には、弥生会計について豊富な知識を有している税理士及び職員がいます。
ご興味がおありでしたら、是非お気軽にお問い合わせください。

法人の税務を承ります
弥生会計を利用されている法人のお客様の税務顧問を承っています。また、リーズナブルな年一決算のみの申告サービスも提供しています。
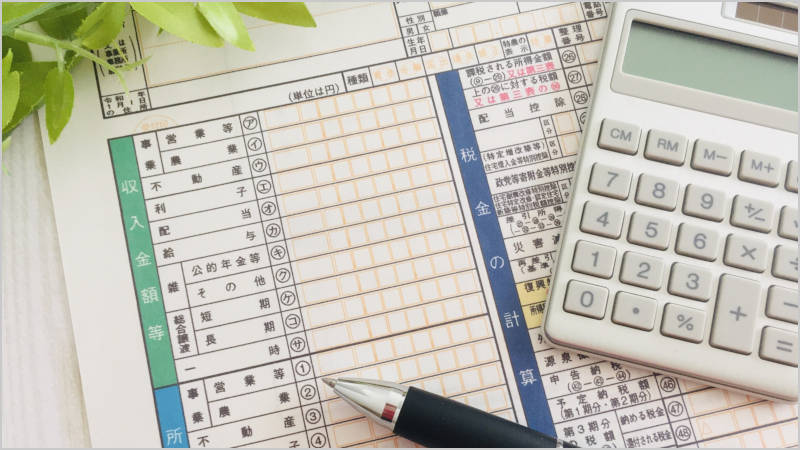
所得税の確定申告を承ります
弥生会計を利用されている法人のお客様の所得税の確定申告を承ります。税理士に直接会わずとも申告ができるサービスを実現しています。

日本全国&海外に対応
フルリモートにつき、日本全国どちらのお客様でも対応可能です。海外在住のお客様にもご愛顧いただいています。(日本法人の日本国内における決算申告を承っています。)

法人設立もサポート
現在、個人事業主の方などこれから法人を設立されるお客様のサポートも承ります。提携している司法書士事務所の協力により相場より安く法人を設立できることもあります。

Webミーティングに対応
面談もWeb会議システムにて承ります。アプリやアカウントは不要です。初回無料相談もリモートで対応可能です。ご要望があれば直接お会いすることもできます。
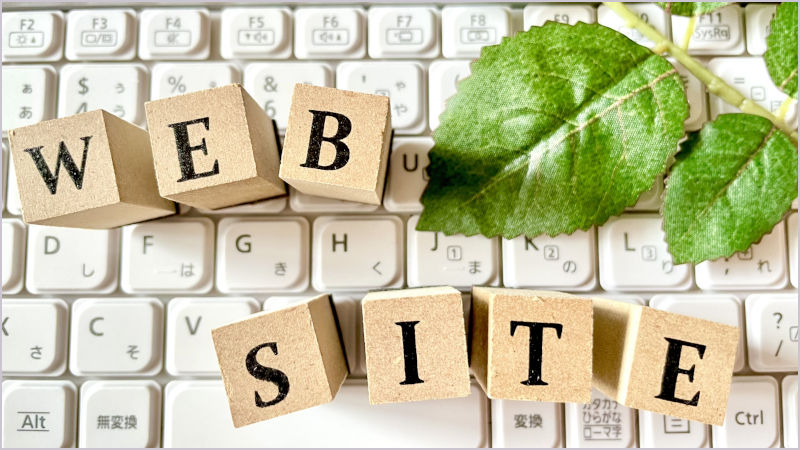
Webサイト作成もサポート
こちらのサイトくらいシンプルな内容のWebサイトであれば格安で構築を支援します。初期費用のみでランニングコストは頂戴しないため安心していただけます。

弥生会計の便利な使い方
弥生会計は多くの税理士が使用している便利な会計ソフトです。弥生会計の便利な使い方を基本的なことから発展的なことまで簡潔に紹介しています。

税理士紹介ナビby弥生
当事務所以外にも弥生会計が得意な税理士の先生方や会計事務所があります。税理士紹介ナビby弥生は弥生公式が税理士を紹介してくれる便利なサービスです。
【法人または個人のお客様】お問い合せ窓口080-7630-0099受付時間 10:00-17:00 [ 土・日・祝日除く ]
メールでのお問い合わせ料金体系
税理士法人加美税理士事務所の税理士川畑英之と申します。
料金体系は次のとおりです。
サービスごとに標準的な料金・費用を記載しています。
【個人の方】
※すべて税抜金額で表示しています。
法人の顧問費用および決算費用
・法人税等(法人税、法人住民税、法人事業税)
| 法人税等 | 売上高 | |||
| 1000万円以下 | 1000万円超 | 2000万円超 | ||
|---|---|---|---|---|
| 2000万円以下 | ||||
| 顧問報酬 | 月額 | 10,000円 | 12,000円 | 15,000円〜 |
| ①年額換算 | 120,000円 | 144,000円 | 180,000円〜 | |
| ②決算報酬 | 40,000円 | 50,000円 | 60,000円〜 | |
| 基本報酬額①+② | 160,000円 | 194,000円 | 240,000円〜 | |
上記が基本的な費用額です。
【年一決算のみ】法人の決算費用
・法人税等(法人税、法人住民税、法人事業税)
| 法人税等 | 売上高 | |||
| 1000万円以下 | 1000万円超 | 2000万円超 | ||
|---|---|---|---|---|
| 2000万円以下 | ||||
| 年一決算報酬 | 140,000円 | 160,000円 | 180,000円〜 | |
・消費税
弥生会計で記帳されているお客様は下記の金額からさらにお値引きいたします。
| 消費税 | 納税額(還付額) | ||
| 100万円以下 | 100万円超 | ||
|---|---|---|---|
| 簡易課税 | 25,000円 | 35,000円〜 | |
| 原則課税 | 一括比例配分 | 35,000円 | 40,000円〜 |
| 全額控除 | 35,000円 | 40,000円〜 | |
| 個別対応 | 40,000円 | 50,000円〜 | |
| 還付申告 | 55,000円 | 65,000円〜 | |
消費税の課税事業者に該当する場合は消費税の申告も必要です。
年間の売上高が1000万円を超える法人は、将来的に課税事業者になる可能性があります。
収入が例年1000万円以下の場合は消費税の申告は不要です。
つまり、上記の消費税の料金も発生しません。
オプション料金
一定の場合にはその他の税務イベントが発生します。
その際は、別途オプションをお申込みいただくことができます。
当該オプション料金・費用についてはこちらのページをご覧ください。
法人設立費用
| 法人設立費用 | |
|---|---|
| 合同会社 | 約13万円 |
| 株式会社 | 約28万円 |
法人設立サポートを適用した場合はもっと安く済むことがあります。
個人の確定申告費用
・所得税
基本的には、従量制です。
例外として金額の規模によっても変動する場合があります。
(例:事業所得、不動産所得、雑所得、譲渡所得)
| 所得税 | |
|---|---|
| 基本料金 | 30,000円 |
| 給与所得(2ヵ所目以降がある場合) | 2,000円/1件 |
| 事業所得 | 50,000円~ |
| 雑所得 | 25,000円~ |
| 不動産所得 | 50,000円~ |
| 一時所得 | 都度見積り |
| 譲渡所得 | 都度見積り |
| 配当所得 | 都度見積り |
| 利子所得 | 都度見積り |
・消費税
| 消費税 | 納税額(還付額) | ||
| 100万円以下 | 100万円超 | ||
|---|---|---|---|
| 簡易課税 | 25,000円 | 35,000円〜 | |
| 原則課税 | 一括比例配分 | 35,000円 | 40,000円〜 |
| 全額控除 | 35,000円 | 40,000円〜 | |
| 個別対応 | 40,000円 | 50,000円〜 | |
| 還付申告 | 55,000円 | 65,000円〜 | |
消費税の課税事業者に該当する場合は消費税の申告も必要です。
年間の売上高が1000万円を超える方は、将来的に課税事業者になる可能性があります。
事業収入が例年1000万円以下の場合は消費税の申告は不要です。
つまり、上記の消費税の料金も発生しません。
【法人または個人のお客様】お問い合せ窓口080-7630-0099受付時間 10:00-17:00 [ 土・日・祝日除く ]
メールでのお問い合わせお問い合わせから申告までの流れ
青字の項目は税理士の担当です。
- お問い合わせ
- お電話、メール、Chatworkのいずれかでお問い合わせください。
※営業時間外の場合はメールかChatworkでお問い合わせいただきますようお願いします。
- Webミーティングの日程調整&参考資料のご送付
- Webミーティングの日程を調整します。
また、過年度の確定申告書や帳簿、定款、登記簿謄本など必要となるものを事前にデータ又は郵送でお送りいただきます。
- Webミーティング(初回無料相談)
- 事業の内容、税務トピック、経理状況をお聞きして、作業ボリューム及び料金を見積もります。
また、税理士とお客様のそれぞれにおいて担当すべき作業を明確に整理します。
- 契約書のご締結&着手金のお振込み
- 契約書をお送りします。
内容に問題がなければご署名ご捺印のうえご返送していただきます。
※契約書は書面、電子のどちらでも対応可能です。(電子契約の方が圧倒的に早いです。)
法人設立に関する届出書一式を提出するなど一定の場合は、併せて着手金を当方の口座にお振込みいただくことがございます。
- 弥生会計及び資料データのご格納(or 紙でのご郵送)
- 弥生会計及び資料データをクラウドストレージ、弥生ドライブまたはスマート証憑管理などご格納いただきます。
または紙のままご郵送いただきます。
- 帳簿完成
- お送りいただいた弥生会計及び資料データに基づいて当方で帳簿を完成させます。
不明な点があればメールやChatworkでご連絡させていただきます。
- 決算のご承認
- 帳簿が完成すると決算書も完成します。
決算書の内容に問題がなければご承認していただきます。
内容については、Webミーティングまたは文面でご説明を申し上げます。
- 確定申告書の作成
- (ご承認いただいた決算書に基づいて)当方で確定申告書を作成します。
- 確定申告書のご承認
- 確定申告書の内容に問題がなければご承認していただきます。
- 電子申告
- 当方で確定申告書を電子申告にて提出します。
- 税金のご納付
- 電子納付または納付書による窓口での納付をしていただきます。
電子納付の場合→電子納付情報を当方からお知らせします。
窓口納付の場合→納付書を当方から郵送します。
- 決算報酬のお振込み
- 決算報酬を当方の口座にお振込みいただきます。
- 成果物の納品
- 最終版の弥生会計データ及び確定申告書一式、決算書、総勘定元帳をデータでご送信します。
【法人または個人のお客様】お問い合せ窓口080-7630-0099受付時間 10:00-17:00 [ 土・日・祝日除く ]
メールでのお問い合わせ【比較】弥生会計と他の会計ソフトの違いとは?税理士が解説!
なぜ弥生会計が多くの税理士事務所・事業者様に選ばれるのか?その理由を分析
会計ソフトにはさまざまな選択肢がありますが、なぜ多くの税理士事務所や事業者様が弥生会計を選んでいるのでしょうか?
1. 業界トップクラスのシェアと信頼性
弥生会計は、累計導入社数が300万社を超える国内最大級の会計ソフトです。多数の他社の申告書作成ソフトとが弥生会計との連携機能を備えていることも大きなメリットです。弥生株式会社が長年培ってきた信頼性と安定性により、多くの税理士事務所や事業者様から支持されています。
2. 税理士との連携がスムーズ
弥生会計は、税理士とスムーズに連携できる設計がされています。データ共有機能やクラウド対応により、事業者様が入力した記帳データを税理士がリアルタイムで確認・修正できます。これにより、税務申告や決算業務がスムーズに進むだけでなく、ミスを防ぐことが可能です。
3. 業種・規模を問わず利用しやすい柔軟なプラン
弥生会計は、小規模事業者様から中小企業まで幅広く対応できるよう、クラウド版とデスクトップ版の両方を提供しています。ニーズに合わせたプラン選択ができるため、事業の成長に応じた活用が可能です。
主要な会計ソフトを比較!弥生会計の強みと他社製品との違い
市場にはさまざまな会計ソフトが存在しますが、それぞれ特徴が異なります。ここでは、代表的な会計ソフトと弥生会計の違いを比較します。
| 会計ソフト | クラウド対応 | 税理士との連携 | 操作のしやすさ | コスト | サポート体制 |
|---|---|---|---|---|---|
| 弥生会計 | ◎(クラウド&デスクトップ) | ◎(税理士と連携しやすい) | ◎(直感的なUI) | ○(コストパフォーマンス良) | ◎(充実したサポート) |
| freee | ◎(クラウドのみ) | ○(税理士対応可能) | ○(シンプル) | △(やや高額) | ○(オンラインサポート) |
| マネーフォワード | ◎(クラウドのみ) | ○(税理士対応可能) | ○(多機能でやや複雑) | △(やや高額) | ○(オンラインサポート) |
| 勘定奉行 | ○(クラウド&オンプレミス) | ○(大企業向け) | △(専門知識が必要) | △(高額) | ◎(手厚いサポート) |
この比較からもわかるように、弥生会計はクラウドとデスクトップの両方に対応し、税理士との連携がスムーズで、操作のしやすさやコスト面で優れている点が特徴です。
弥生会計はどんな業種・規模に最適?中小企業・個人事業主の活用事例を紹介
1. 小規模事業者・個人事業主様の事例
飲食店、美容室、フリーランスの方など、個人事業主様にとっては、日々の記帳作業を簡単に行える点が弥生会計の魅力です。特に「かんたん取引入力」機能を活用することで、簿記の知識がなくてもスムーズに経理処理ができます。
2. 中小企業の事例
中小企業では、弥生会計の「部門管理機能」や「固定資産管理機能」を活用し、経営の意思決定に役立つデータをリアルタイムで把握できます。また、給与計算ソフト「弥生給与」との連携により、給与計算業務の効率化も可能です。
3. 税理士との連携による業務効率化
多くの税理士事務所では、弥生会計を導入することで、事業者様とのデータ共有がスムーズになり、申告書の作成や税務相談がより迅速に行えるようになります。
まとめ
弥生会計は、多くの税理士事務所や事業者様に選ばれる理由が明確な会計ソフトです。他社製品と比較しても、コストパフォーマンスの良さや税理士との連携のしやすさが際立っており、特に中小企業や個人事業主様にとって強力なサポートツールとなります。
会計ソフトの選択に迷われている方は、弥生会計の導入をぜひ検討してみてください。税理士と連携することで、より効率的な経理業務が実現できるでしょう。
弥生会計のクラウド版 vs デスクトップ版!税理士が選び方を徹底比較
クラウド版とデスクトップ版の違いとは?税理士が選び方を徹底解説
弥生会計には、大きく分けて「クラウド版(弥生会計 オンライン)」と「デスクトップ版(弥生会計 25など)」の2種類があります。それぞれ特徴が異なり、事業者様の業態や経理の運用体制に応じて適切な選択が求められます。
| 特徴 | クラウド版 | デスクトップ版 |
|---|---|---|
| データ管理 | クラウド上で管理 | ローカルPCに保存 |
| アクセス | どこからでも可能 | 1台のPCに依存 |
| 税理士との共有 | 簡単にリアルタイム共有可能 | データ送付が必要 |
| コスト | 月額課金制 | 買い切り型(年額サポートあり) |
| 機能面 | 必要最低限の機能が揃っている | 高度な会計処理が可能 |
弥生会計クラウド版のメリット・デメリット|オンライン対応・業務効率化の視点から分析
メリット
- どこでもアクセス可能
- インターネット環境があれば、オフィスや自宅、外出先でも利用可能。リモートワークにも最適です。
- 税理士と簡単にデータ共有できる
- 記帳データを税理士とオンラインで共有でき、リアルタイムでチェックや修正が可能。
- 自動バックアップ機能
- クラウド上でデータを管理するため、PCトラブルや災害時のデータ損失リスクが低減。
デメリット
- インターネット環境に依存
- ネットワーク環境が不安定だと、作業効率が低下する可能性があります。
- 機能面の制約
- デスクトップ版と比較すると、固定資産管理や詳細な部門管理など一部の高度な機能が制限されます。
- 月額課金制
- 利用期間が長くなると、買い切り型のデスクトップ版に比べてコストがかさむ可能性があります。
デスクトップ版はどんな事業者様に最適?安定性・機能面から徹底比較
デスクトップ版のメリット
- オフライン環境でも利用可能
- インターネット接続がなくても作業ができるため、安定した環境で業務が可能。
- 多機能で高度な会計処理が可能
- 製造業や経理業務の細かい処理が必要な中小企業に適しています。
- 買い切り型で長期的にコストが安くなる
- 一度購入すれば、年間サポート費用のみで利用可能。長期的なコストを抑えられます。
デスクトップ版のデメリット
- PCの故障リスク
- データがローカルに保存されるため、PCが故障するとデータ復旧が困難になる可能性があります。
弥生ドライブなどのクラウドストレージにデータを保存しておくとこのデメリットを回避することができます。
- 税理士とのデータ共有が手間
- クラウド版と異なり、データを送付する必要があるため、リアルタイムの確認が難しくなります。
弥生ドライブなどのクラウドストレージにデータを保存しておくとこのデメリットも回避することができます。
- リモートワークには不向き
- 会社のPCでのみ作業可能なため、外出先や自宅からの利用が難しい。
会社用のラップトップを持ち出せる場合はこのデメリットを解決することができます。
税理士との連携を考慮した場合の最適解|弥生会計の活用ポイント
税理士との連携を考慮すると、クラウド版が有利です。以下のポイントを踏まえ、最適な選択を行いましょう。
- 税理士とのリアルタイム共有が必要な場合 → クラウド版が最適
- 固定資産管理や部門別会計など詳細な処理が必要な場合 → デスクトップ版が適している
- コストを抑えつつシンプルな経理処理をしたい場合 → クラウド版の月額プランがおすすめ
- オフラインでも作業したい場合 → デスクトップ版が有利
結論:どちらを選ぶべき?
- フリーランスの方や小規模事業者様で、税理士とのデータ共有をスムーズにしたい場合 → クラウド版
- 中小企業で、経理業務の複雑な処理や安定した環境を求める場合 → デスクトップ版
最適な選択をするために、税理士と相談しながら導入を進めることが重要です。
弥生会計と税理士の連携で業務効率化!導入・運用のポイントを徹底解説
弥生会計と税理士の連携がもたらす業務効率化のメリットとは?
弥生会計を活用し、税理士と連携することで、経理業務の効率化が大幅に向上します。特に、中小企業や個人事業主様にとって、経理の手間を軽減しつつ正確な会計処理を実現するためには、税理士のサポートが重要です。
1. 記帳・仕訳の自動化で作業時間を削減
弥生会計には、銀行やクレジットカードと連携することで、自動で仕訳を行う機能が搭載されています。これにより、手作業での入力ミスを防ぎ、経理業務の負担を軽減できます。税理士と連携すれば、仕訳のチェックや修正もスムーズに行え、正確な財務データを維持できます。
2. クラウド機能でリアルタイム共有が可能
クラウド版の弥生会計を利用すれば、事業者様と税理士がリアルタイムでデータを共有できます。これにより、
- 月次決算や申告準備の進行状況をリアルタイムで確認
- 修正が必要な取引データをその場でアドバイス
- 申告前のデータ確認がスムーズ
といったメリットがあります。
3. 税務リスクの軽減と正確な申告
税理士と連携することで、税務調査に耐えうる正確な記帳・申告が可能になります。誤った仕訳や控除漏れを防ぎ、税務リスクを最小限に抑えることができます。
4. 資金調達や経営判断に活かせる財務データの最適化
適切な記帳と正確な財務データがあれば、銀行や投資家への説明が容易になります。税理士が定期的に財務状況をチェックすることで、資金繰りや節税対策の提案が可能になります。
弥生会計の導入で税理士とのスムーズな連携を実現する方法
弥生会計と税理士の連携を最大限に活かすためには、以下のポイントを押さえて導入・運用することが重要です。
1. 税理士と事前に運用ルールを決める
弥生会計を導入する際は、税理士とどのようにデータを管理・共有するのか事前にルールを決めておくと、スムーズに業務を進められます。
- 記帳作業の分担(事業者様が入力する範囲、税理士がチェックする範囲)
- データの共有方法(クラウド版ならリアルタイム、デスクトップ版ならデータ送付)
- 月次決算や申告準備のスケジュール設定
2. クラウド版を活用した効率的なデータ共有
弥生会計クラウド版を利用すると、税理士とのデータ共有が格段に楽になります。具体的には、
- 記帳データのオンライン共有
- 税理士がリアルタイムで帳簿を確認・修正
- 記帳ミスの早期発見と修正が可能
クラウドを活用することで、税理士とのやり取りがスムーズになり、決算や確定申告の準備が短縮されます。
3. デスクトップ版でも税理士との連携を工夫
デスクトップ版を使用する場合は、税理士にデータを送付する必要があります。以下の方法を活用すると、連携がスムーズになります。
- 定期的にデータをエクスポートし、税理士へ送付
- 弥生ドライブ、DropboxやGoogle Driveなどのクラウドストレージを活用
- 弥生会計の「データ共有機能」を利用
4. 定期的なミーティングで業務フローを見直す
税理士と定期的にオンラインミーティングや対面での面談を行うことで、
- 記帳の問題点や改善点を明確にする
- 最新の税務情報を事業者様が把握できる
- 経営状況をリアルタイムで確認し、最適なアドバイスを受けられる
5. 会計業務を一元管理し、業務効率を最大化
弥生会計には給与計算や請求書作成機能もあり、会計業務を一元管理できます。税理士と連携することで、
- 給与計算や年末調整の確認
- 資金繰りや節税対策の提案
- 確定申告や決算書作成の効率化
といった効果を期待できます。
まとめ
弥生会計を導入し、税理士と連携することで、記帳の正確性向上、業務の効率化、税務リスクの軽減など多くのメリットが得られます。
特に、クラウド版を活用することで、税理士とのデータ共有がスムーズになり、経理業務の負担が大幅に軽減されます。
事業者様が安心して経営に専念できるよう、弥生会計を最大限活用し、税理士と密に連携していきましょう。
弥生会計の導入や税理士との連携についてご相談がある場合は、お気軽にお問い合わせください。
フリーランス・個人事業主必見!弥生会計を使った記帳・確定申告のコツ
フリーランス・個人事業主が知っておくべき弥生会計の基本機能とは?
フリーランスや個人事業主にとって、経理業務は本業と並行して行わなければならない重要な業務です。しかし、専門知識がないと、記帳や確定申告の準備が負担になりがちです。弥生会計を活用することで、初心者でも簡単に経理作業を進めることができます。
1. かんたん取引入力機能で記帳をスムーズに
弥生会計には「かんたん取引入力」機能があり、
- 取引の種類を選ぶだけで自動で仕訳が行われる
- 複雑な簿記の知識がなくても簡単に記帳できる
- 取引内容を選択し、金額を入力するだけで帳簿が作成される
といった利便性があります。
2. 銀行明細の自動取得で手入力の手間を削減
弥生会計では、銀行やクレジットカードの取引データを自動で取り込み、仕訳処理を簡単に行えます。これにより、
- 記帳の手間を大幅に削減
- 入力ミスの防止
- キャッシュフローの可視化
が実現できます。
3. 仕訳辞書機能でルーチン業務を効率化
頻繁に発生する取引は仕訳辞書に登録しておくことで、自動で仕訳を適用できます。例えば、
- 毎月の家賃支払いや光熱費を登録
- クライアントごとの請求書処理を自動化
- 仕訳の手間を削減し、業務効率化
といった使い方が可能です。
弥生会計で簡単にできる記帳・仕訳作業のコツ|経理初心者でも安心!
1. 記帳のルールを決めて習慣化する
経理業務をスムーズに進めるためには、日々の記帳を習慣化することが大切です。
- 毎日、または週に一度、定期的に記帳を行う
- レシートや領収書をスマホで撮影・保存し、弥生会計に取り込む
- クラウド版を活用して、外出先でも記帳できる環境を整える
2. 勘定科目を適切に選ぶ
弥生会計では、適切な勘定科目を選択することで、
- 正しい帳簿を作成できる
- 確定申告時に税務リスクを軽減できる
- 経費の計上漏れを防ぐ
といったメリットがあります。
3. 取引先や経費の分類を整理
取引ごとにカテゴリーを分けて管理することで、
- 確定申告時に必要なデータをスムーズに抽出できる
- 不要な経費の見直しがしやすくなる
- 収支のバランスを把握しやすくなる
といった経営管理の向上につながります。
確定申告をスムーズに!弥生会計を活用した効率的な申告方法を解説
確定申告は、フリーランスや個人事業主にとって避けて通れない業務です。弥生会計を活用することで、確定申告の手続きを効率化できます。
1. 青色申告と白色申告の違いを理解する
弥生会計は青色申告・白色申告のどちらにも対応していますが、青色申告を選ぶことで、
- 65万円の特別控除が受けられる
- 家族への給与を経費として計上できる
- 損失を3年間繰り越せる
といった税制上のメリットがあります。
青色申告についてより詳しい解説は下記のページをご覧ください。
2. 弥生会計で確定申告書を作成する方法
弥生会計を使えば、
- 年間の収支データを整理(日々の記帳が申告時に活きる)
- 決算書を自動作成(損益計算書や貸借対照表を自動生成)
- 確定申告書を作成(税務署に提出する書類を自動で作成)
という流れで簡単に確定申告を行えます。
3. 電子申告(e-Tax)で手続きを簡略化
弥生会計はe-Taxにも対応しているため、
- 確定申告書をオンラインで提出可能
- 税務署に行く手間を省ける
- 迅速な税務処理が可能
といったメリットがあります。
4. 税理士との連携でスムーズな申告を実現
フリーランスや個人事業主が税務申告を正確に行うためには、税理士との連携が有効です。
- 申告前に帳簿をチェックしてもらう
- 節税対策のアドバイスを受ける
- 税務調査のリスクを軽減する
といったメリットがあり、より安心して申告ができます。
まとめ
弥生会計を活用することで、フリーランスや個人事業主の経理業務を大幅に効率化できます。
- 記帳の手間を削減し、正確な帳簿を作成
- 確定申告をスムーズに進めるための機能を活用
- 税理士と連携し、最適な節税対策を実施
特に、弥生会計の「かんたん取引入力」や「銀行明細の自動取得」機能を活用することで、初心者でもスムーズに経理業務を進められます。
確定申告や経理業務に不安がある方は、ぜひ税理士に相談しながら、弥生会計を最大限に活用しましょう!
税理士に相談すべき?弥生会計で経理を自計化するメリット・デメリット
弥生会計で経理を自計化するメリットとは?コスト削減と業務効率化のポイント
弥生会計は、フリーランスの方や個人事業主様から中小企業まで幅広く利用されており、経理業務を自社で行う「自計化」に最適な会計ソフトです。ここでは、自計化のメリットについて解説します。
1. コスト削減が可能
税理士に記帳代行を依頼すると、顧問料や記帳代行費用が発生しますが、弥生会計を活用すれば、これらのコストを削減できます。
- クラウド版を利用すれば、会計データをオンラインで管理可能。
- 月額プランを選択することで、低コストで経理業務を運用。
- 必要に応じて税理士にスポット相談をすることで、コストを最適化。
2. 経理業務の可視化と業務効率化
自計化することで、
- 収支状況をリアルタイムで把握。
- 経理の流れを理解し、適切な資金管理が可能。
- 経費の適切な計上で節税対策がしやすくなる。
弥生会計には「かんたん取引入力」や「自動仕訳」機能があり、簿記の知識がない方でもスムーズに経理業務を進められます。
3. 事業の成長に応じた柔軟な経理対応
事業が成長すると、経理業務の複雑さも増します。弥生会計のクラウド版を活用すれば、
- 事業規模に応じて会計処理をカスタマイズ。
- 経営状況をリアルタイムで確認し、迅速な経営判断が可能。
- 必要に応じて税理士と連携し、サポートを受けられる。
自計化で気をつけるべきデメリット|税務リスクや時間の負担を回避する方法
自計化には多くのメリットがありますが、一方でリスクや負担も考慮する必要があります。
1. 記帳ミスによる税務リスク
税務申告において、
- 記帳ミスが発生すると、税務調査の対象になりやすい。
- 誤った仕訳によって、控除漏れや過少申告のリスクが生じる。
- 税務調査時に適切な対応ができず、追徴課税が発生する可能性がある。
対策:
- 弥生会計の「自動仕訳」機能を活用し、仕訳ミスを最小限に。
- 定期的に税理士にチェックを依頼し、記帳ミスを防ぐ。
2. 時間的な負担が増える
経理を自社で行うことで、
- 毎月の記帳や仕訳に時間を取られる。
- 確定申告や決算処理に多くの時間を費やす必要がある。
- 本業に集中できず、業務効率が低下する可能性がある。
対策:
- 弥生会計の「銀行明細自動取得」や「請求書連携機能」を活用し、手間を削減。
- 月次で経理時間を確保し、計画的に作業を進める。
3. 税法の変更に対応が必要
税法は頻繁に改正されるため、最新の税務情報を把握することが重要です。
- 消費税の適用ルールや控除の変更に対応できないと、正確な申告が困難に。
- 経費の計上ルールを誤ると、税務リスクが高まる。
対策:
- 税理士と連携し、最新の税制情報を適用。
- 税務セミナーやオンライン講座で基礎知識を習得。
インボイス制度を含めた消費税についてより詳しい解説は下記のページをご覧ください。
税理士に相談するべきケースとは?弥生会計の活用で最適な経理体制を構築
すべての経理業務を自社で行うのではなく、必要に応じて税理士に相談することで、効率的な経理体制を築くことができます。
1. 税務申告や決算書の作成が難しい場合
弥生会計を活用して記帳業務は自社で行い、
- 決算書の作成や申告業務は税理士に依頼。
- 節税対策を含めたアドバイスを受ける。
2. 節税対策を最大限に活用したい場合
税理士と連携することで、
- 青色申告の特典を最大限活用。
- 法人化のタイミングを適切に判断。
- 役員報酬や設備投資の最適な計画を立てる。
3. 税務調査リスクを回避したい場合
税務調査は、記帳ミスや過少申告が原因で行われることが多いです。
- 税理士がチェックすることで、誤りを未然に防ぐ。
- 申告書の作成を依頼し、税務リスクを軽減。
税務調査に関するより詳しい解説は下記のページをご覧ください。
まとめ
弥生会計を活用して経理を自計化することで、コスト削減や業務効率化が可能ですが、記帳ミスや税務リスクの負担も発生します。
自計化のメリット
- コスト削減が可能
- 経理業務を可視化し、経営判断に活用
- 事業の成長に合わせて柔軟な対応が可能
自計化のデメリットと対策
- 記帳ミスによる税務リスク → 税理士の定期チェックを活用
- 時間的負担が増える → 弥生会計の自動化機能を活用
- 税法改正への対応が必要 → 税理士から最新情報を得る
税理士に相談すべきケース
- 税務申告や決算の作成が難しい場合
- 節税対策を最大限に活用したい場合
- 税務調査リスクを回避したい場合
自計化を進めるにあたり、弥生会計の機能をフル活用し、必要な場面では税理士と連携することで、最適な経理体制を構築しましょう。
顧問契約するべき?弥生会計を最大限活用するための税理士の役割
税理士と連携するメリット|記帳・決算・節税対策のサポートを徹底解説
弥生会計は、フリーランスの方や個人事業主様、中小企業の経理業務を効率化する優れた会計ソフトですが、正確な記帳や適切な節税対策を行うには、税理士との連携が重要です。税理士を顧問として契約することで、弥生会計の機能を最大限に活かし、経理業務の負担を軽減できます。
1. 記帳業務の効率化と正確性の向上
弥生会計には「自動仕訳」や「銀行明細自動取得」などの機能がありますが、税理士と連携することで以下のメリットがあります。
- 仕訳のチェックを行い、記帳ミスを防ぐ
- 勘定科目の適用を最適化し、税務リスクを軽減
- 経理のルールを整備し、継続的な業務効率化を実現
2. 決算・確定申告のスムーズな対応
決算時や確定申告の際に、税理士がサポートすることで以下のメリットがあります。
- 正確な決算書の作成を支援
- 法人税・所得税・消費税の適切な申告
- 申告ミスを防ぎ、税務調査リスクを最小限に
3. 節税対策のアドバイス
税理士と連携することで、
- 適用可能な税制優遇措置の提案
- 減価償却の適切な計上で税負担を軽減
- 役員報酬・退職金の最適な設定
といった具体的な節税対策が可能になります。
節税対策に関するより詳しい解説は下記のページをご覧ください。
弥生会計×税理士の活用で業務効率化!経理負担を軽減する方法とは?
1. クラウド版や弥生ドライブを活用したリアルタイム共有
弥生会計クラウド版や弥生ドライブを活用すれば、
- 事業者様と税理士がリアルタイムでデータ共有
- 記帳内容の即時確認と修正
- 決算・申告業務の準備を前倒しで進行
といったメリットがあります。
2. 経理業務の分担で負担を軽減
弥生会計を活用することで、
- 日常の記帳業務は事業者様が対応
- 月次決算や仕訳のチェックは税理士が担当
- 年末調整や確定申告は税理士が代行
といった役割分担が可能になり、経理の負担を軽減できます。
3. 顧問契約での定期的なアドバイス提供
税理士との顧問契約を結ぶことで、
- 最新の税務情報の提供
- 経営状況に応じた節税・財務アドバイス
- 事業拡大に向けた財務戦略のサポート
といった長期的な視点での経営支援を受けることができます。
顧問契約の費用対効果は?税理士のサポート範囲と活用ポイントを紹介
1. 顧問契約の主な内容
税理士との顧問契約には、以下のようなサポート内容が含まれることが一般的です。
- 記帳指導・仕訳チェック
- 決算・確定申告の対応
- 税務相談・節税対策の提案
- 税務調査時の対応
2. 顧問契約の費用相場
税理士の顧問契約費用は、
- フリーランス・個人事業主:月額1万円~3万円程度
- 中小企業(年間売上1億円未満):月額3万円~5万円程度
- 中規模企業(年間売上1億円以上):月額5万円~10万円程度
事業規模や業務内容によって費用が異なりますが、適切な顧問契約を結ぶことで、
- 節税額が顧問料を上回るケースが多い
- 税務調査時のリスクを最小限に抑えられる
- 経営に専念できる環境が整う
といった効果が期待できます。
3. 顧問契約を活用するポイント
- クラウド版や弥生ドライブを活用し、リアルタイムで税理士と連携
- 月次などの一定のタイミングで税理士とミーティングを実施し、財務状況を把握
- 節税や融資相談など、長期的な視点でサポートを受ける
- 税務調査に対する不安を払拭する
まとめ
弥生会計を最大限活用するためには、税理士との連携が重要です。顧問契約を結ぶことで、
- 記帳業務の正確性向上
- 決算・申告のスムーズな対応
- 節税対策の最適化
- 経営に関するアドバイスの提供
などのメリットが得られます。 - 税務調査のリスクを抑える記帳や証憑管理を実施
事業規模に応じて適切な顧問契約を結び、弥生会計を活用しながら、税理士と共に経営を安定させましょう。
顧問契約についてのご相談は、ぜひお気軽にお問い合わせください。
【中小企業向け】弥生会計を活用した資金調達・融資のポイントとは?
資金調達に強い企業になる!弥生会計で金融機関の信用を高める方法
中小企業が安定した経営を続けるためには、資金調達のスムーズな実施が欠かせません。弥生会計を活用することで、金融機関からの信用を高め、融資審査を有利に進めることが可能です。
1. 正確な財務データの記録と管理
金融機関が融資審査の際に重視するのは、財務データの正確性と透明性です。弥生会計を利用することで、日々の会計処理を正しく行い、最新の財務状況を常に把握できます。
- リアルタイムで収支を管理し、資金繰りを可視化。
- 自動仕訳機能を活用し、入力ミスを防止。
- 金融機関が求める決算書・試算表を簡単に作成可能。
2. キャッシュフロー管理の強化
融資審査では、企業のキャッシュフローが健全かどうかが重要視されます。弥生会計を活用して、現金の流れを明確にし、適切な資金管理を行いましょう。
- 収支レポートを定期的に作成し、資金計画を立てる。
- 売掛金・買掛金の管理を強化し、回収漏れを防ぐ。
- クラウド版ならリアルタイムで資金状況を把握できる。
3. 信頼性の高い財務資料の作成
金融機関への融資申請時に、正確な財務資料を提出できるかが大きなポイントとなります。
- 貸借対照表や損益計算書を正確に作成。
- 財務データを視覚的に整理し、融資担当者に伝わりやすく。
- 税理士と連携し、専門家のチェックを受けることで信頼性を向上。
弥生会計を活用し、金融機関からの信用を高めることで、資金調達の成功率を大幅に向上させることが可能です。
補助金・助成金の申請にも活用!弥生会計で正確な財務管理を実現
中小企業にとって、補助金や助成金は事業運営の強力なサポートになります。弥生会計を活用することで、スムーズな申請手続きが可能になります。
1. 申請に必要な財務データの準備
補助金・助成金の申請では、過去の財務データや事業計画の提出が求められることが多くあります。
- 正確な決算書・損益計算書の作成。
- 補助金申請に必要な経費データをカテゴリ別に管理。
- 弥生会計のレポート機能を活用し、データを整理。
2. 補助金・助成金の活用可能な経費の管理
多くの補助金・助成金では、特定の経費のみが対象となります。そのため、会計ソフトを活用して適切に分類することが重要です。
- 対象経費を正しく仕訳し、申請要件を満たすように整理。
- 税理士と連携し、誤った経費計上を防ぐ。
- クラウド版を活用し、申請データをリアルタイムで共有。
3. 申請後の報告義務に対応するための記帳管理
補助金や助成金の受給後も、定期的な報告が求められるケースがあります。弥生会計を活用し、適切な管理を行いましょう。
- 補助金の使途を正確に記録し、適正な報告を実施。
- 定期的な帳簿の見直しを行い、適切な運用を継続。
- 税理士と連携し、監査対応にも備える。
弥生会計を適切に活用することで、補助金・助成金の申請プロセスをスムーズにし、事業の安定成長を支えることができます。
まとめ
資金調達や補助金・助成金の活用において、弥生会計は強力なツールとなります。
- リアルタイムの財務管理で金融機関の信用を向上。
- キャッシュフローを適切に管理し、資金繰りを最適化。
- 補助金申請に必要なデータを整備し、スムーズな申請を実現。
- 税理士と連携し、正確な財務情報を維持。
弥生会計を最大限活用し、資金調達を成功に導く体制を整えましょう。資金調達や補助金活用についてのご相談は、お気軽にお問い合わせください。
【事業者様向け】弥生会計×税理士の最適な活用法と成功事例
記帳・決算・税務申告をスムーズに!弥生会計を活かす税理士の役割
弥生会計を導入することで、記帳・決算・税務申告の業務を効率化できます。しかし、よりスムーズに運用するためには、税理士との連携が欠かせません。
1. 記帳の正確性を向上させる
弥生会計には仕訳の自動入力機能や連携機能がありますが、会計知識が不足しているとミスが発生することも。税理士が定期的にデータをチェックすることで、記帳の正確性を向上させることが可能です。
2. 決算業務を効率化する
決算時には、経費の計上や減価償却の処理など、専門知識が必要な作業が発生します。税理士が関与することで、スムーズに決算を完了し、税務リスクを最小限に抑えられます。
3. 税務申告のミスを防ぐ
税務申告には多くのルールがあり、誤った申告をすると修正申告が必要になるだけでなく、ペナルティが発生することも。税理士と連携することで、正確な申告が可能になります。
自計化と税理士のハイブリッド運用|弥生会計を最大限に活かす方法
「経理をすべて自社で行うべきか、それとも税理士に依頼すべきか?」という悩みを持つ事業者様は多いです。弥生会計を活用すれば、自計化と税理士のハイブリッド運用が可能になります。
1. 日々の記帳は自社で対応
日々の売上や経費の入力は自社で行うことで、コストを削減しつつ、リアルタイムで財務状況を把握できます。弥生会計の自動仕訳機能を活用すれば、作業時間の短縮も可能です。
2. 月次・四半期ごとに税理士がチェック
税理士が定期的にデータをチェックし、仕訳ミスの修正や節税対策のアドバイスを提供します。この仕組みにより、経理を効率的に運用できます。
3. 決算・申告は税理士に依頼
決算業務や税務申告は専門知識が必要なため、税理士に依頼することでミスを防ぎ、適切な節税対策を実施できます。
成功企業に学ぶ!弥生会計を活用した経理改善事例を紹介
ケース1:Excelから弥生会計へ移行し、作業時間を50%削減
ある小規模製造業では、Excelで作成した帳簿を使って経理を行っていました。しかし、弥生会計を導入し、税理士のアドバイスを受けながら自計化を進めた結果、記帳作業の時間を50%削減し、経理担当者の負担を大幅に軽減できました。結果として新たに発生した弥生会計のソフトウェア代の元を取ることができました。
ケース2:税理士との連携で税務調査リスクを低減
中小企業のA社では、過去の税務調査で指摘を受けた経験がありました。しかし、弥生会計を導入し、税理士と連携することで、正確な記帳と申告を実現。結果として、その後の税務調査では問題なく対応できるようになりました。
【法人または個人のお客様】お問い合せ窓口080-7630-0099受付時間 10:00-17:00 [ 土・日・祝日除く ]
メールでのお問い合わせ